2024.07.23
クールで静かな子ども、それってもしかすると愛着障害かも??
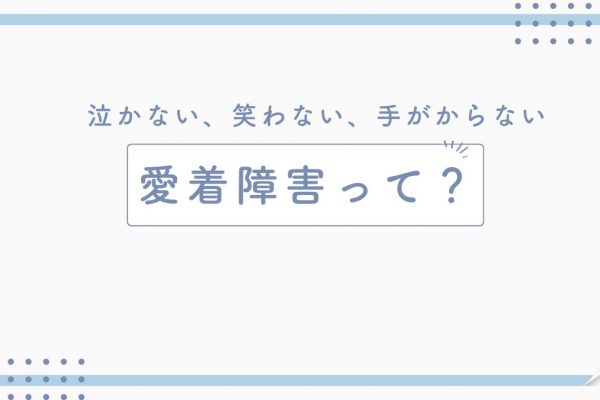
愛着障害をご存知ですか?
愛着障害とは笑わない・目を合わせないなどの症状が子どもに出てしまう障害のことをいいます。
今回は愛着障害について紹介します。
そもそも「愛着」とはなにか?
 引用:写真AC
引用:写真AC
愛着とは、乳幼児期の子どもと養育者の間で気づかれる心理的な結びつきのことを言います。
子どもは生後3ヶ月位までは人の区別がつかず誰に対しても微笑んだり、見つめたりします。
しかし、だんだん自分が欲求を訴えて泣く時に駆け寄ってきてくれる特定の人を認識するようになるのです。
「この人は自分によく声をかけてくれるし、抱っこしてくれる」など特定の人を養育者として認識するようになってきます。
そしてその人との間に愛着が生まれるのです。
なぜ愛着が必要なのか?
愛着には大きく分けて3つの意味があると言います。
人への基礎的信頼感の芽生え
子どもにとって生まれて初めての親しい他者との関わりになるため、この愛着によって人と関わる楽しさや喜びを体験します。
自己表現力・コミュニケーション能力を高める
愛着を形成した人との関わりは、自分の要求を伝え時に相手の要求を受け入れるということを学ぶ機会になります。
これにより表現力やコミュニケーション能力の向上が期待できます。
自己の存在と安全を確保する
子どもが好奇心や積極性、ストレスに耐える力を身につけるために必要な場所になります。
子どもは不安や危機を感じた時に、愛着の対象者を「安全基地」と見なして、自分の身を守ろうとします。
安全基地とは子どもが拠り所とする存在を指します。なにかストレスを感じた時に心の拠り所とする場所が安全基地です。
愛着障害とは?
 引用:写真AC
引用:写真AC
ここまで愛着に付いて紹介してきましたが、愛着障害になるとどんな症状が出てしまうのでしょうか?
愛着障害には2種類あるといいます。
「反応性アタッチメント障害(反応性愛着障害)」と「脱抑制型愛着障害」です。
どちらも、5歳以前に発症するとされており、下の2点によって、見分けることができます。
〇人に対して過度に警戒する・・・「反応性アタッチメント障害(反応性愛着障害)」
〇過度になれなれしい・・・「脱抑制型愛着障害」
ではここからは1つ1つどんな症状が出るのかみていきましょう。
「反応性アタッチメント障害(反応性愛着障害)」について
・養育者へ安心や慰めを求めるために抱きついたり、泣きついたりすることがほとんどない(つらいときも甘えない)
・笑顔が見られず、無表情なことが多い
・他の子どもに興味を示さない、交流しようとしない など
「脱抑制型愛着障害」について
・ほとんど知らない人に対してもなんのためらいもなく近づく
・知らない大人に抱きつき、慰めを求める
・落ち着きがなく、乱暴 など
このような症状が現れるそうです。またどちらにも現れる症状も存在します。
どちらの愛着障害にも見られることとして、強情・意地っ張り・わがまま、といった態度が挙げられます。
いずれも子どもと養育者との愛着形成が不安定であることによって起こるので、愛着障害の子どもは養育者を頼りにし、甘えることが上手にできません。
そのため意地っ張りになってしまったり、極度にわがままになってしまったりすることがあります。
愛着障害の原因
愛着障害の原因は、子どもと養育者との間に愛着がうまく形作られないことが大きく関係しています。具体的には、以下のような原因が挙げられます。
・養育者との死別・離別
・養育者から虐待やネグレクト
・養育者が子どもに対して最低限の世話はするものの、無関心であったり放任したりしていた
・養育者のような立場の大人が複数いて、世話を焼いてくれる人が頻繁に変わってしまっていた
・兄弟差別など、他の子どもと明らかに差別されて育てられた
このように、本来愛着を形成する対象に危害を加えられたり、それによって自分が育った環境が安全でなかったりすると愛着の形成が阻害されてしまいます。
スマホが愛着障害を引き起こしてしまうかも!?
 引用:写真AC
引用:写真ACスマホには豊富な情報が溢れていて楽しい情報もたくさんあります。
育児ストレスから逃れ、ママ友と通話やチャット・ゲームをするというママも。
でも、子どもからの問いかけや話しかけについつい空返事で答えていませんか?
これをつづけると、子どもは自分の感情を閉じ込め無表情なサイレントベビーになります。
親に無視され続けてきたサイレントベビーは、孤立を好み、人間関係が築けず、強制的に関係を持とうとすると断固拒否するといいます。
そしてこの愛着障害がおとなになってからも続いてしまうこともあり、大人になってもなお続いてしまうことは珍しいことではないのです。
ぜひ一度スマホから目を話して、子どもからの問いかけに耳を澄ませてみてください。養育者だからこそ子どもは何かを話しかけてくれているかもしれません。
HERTH PRESS「育児中の「スマホに夢中」が「サイレントベビー」を生む?」
マドレクリニック「愛着障害」

mamaPRESS編集部
mamaPRESS編集部です!“「ママ」であることをもっと楽しみたい!輝きたい!”そんなママたちのために「ママ」が知りたい情報だけをお届けしています。mamaPRESSを読むことで、心に...
詳しくはこちら







