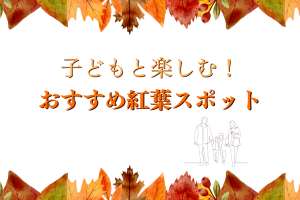5月生まれベビーの“得する?損する?”リアル

5月生まれのお子さんって、“産まれ月がちょうどいい”って、本当?
5月生まれは、一つの学年の中では「お兄さん」「お姉さん」になる生まれ月。
学年の中でも産まれが早いために、同じ学年でも優位性があるという考え方があります。
お子さんの成長は人それぞれなので、そこまで気にしないという方が大半ですが、保活のタイミングや、産後の季節で過ごしやすさが変わってくるという意見もあります。
よく聞く「5月生まれベビーは得する?」という疑問について今回は少し掘り下げてみたいと思います。
 引用:ちょうどいいイラスト
引用:ちょうどいいイラスト得するケース
季節の変わり目の4月ごろは、だんだんと春が近づき過ごしやすくなります。
その一方で朝晩の気温差が激しかったり、日によってなかなか気温が定まらなかったりすることも。
しかし5月に入る頃には気候が安定し、ぽかぽかとした日が続くようになるので産後のママや赤ちゃんにとって過ごしやすい時期といえます。
また、冬のようにインフルエンザなどに感染する可能性が低く、感染症への罹患や風邪の心配が少ないこともメリットです。
これに加えよく言われるのが、5月生まれの子どもは同学年の子どもに比べて生まれが早い方になるので、できることが多かったり理解力が高かったりするというもの。
子どもの発達には個人差が大きくあるので一概には言えませんが、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
育休から復帰タイミングと保育園へ通うタイミングも、悩ましいところですよね。
子供を預けられるのは、生後57日目からと定められています。
とはいっても、都内などの認可保育園は年度途中でのほとんど空きがないので、毎年4月の一斉入園の時期に応募して入るしかありません。その際は、年齢別のクラスに申し込みます。
多くの保護者は、「0歳児クラス」か「1歳児クラス」に申し込みますが、実は「0歳児クラス」の方が倍率は低いため、狙い目と言われています。
5月産まれは、4月時点で0歳児になるので、倍率が少ないということで、申込しやすいと考える風潮があるようです。
しかし、最近は0歳児クラスも倍率が高くなっているようなので、0歳児クラスを狙うことが出来れば確実とは言えなくなってきてしまっています。
自治体で事前にヒアリングを行い、「年齢別の倍率」を聞いておくようにしましょう。
このほかにも年度の後半に生まれた赤ちゃんを4月に預けようとすると、赤ちゃんと過ごせる時間が十分にもてないこともありますが
5月生まれという年度の前半に出産すると1年近く赤ちゃんと過ごした後保育園に預けることが出来るというメリットもあります。
ただ、5月産まれだから、絶対得という訳ではなく、デメリットも勿論あります。
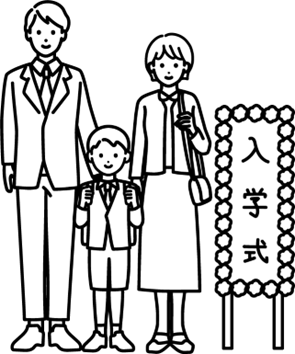 参照:ちょうどいいイラスト
参照:ちょうどいいイラスト損するケース
・生後2~3カ月の頃に梅雨~猛暑を迎えるため、冷房の使い方などにすごく気を使ってしまう。
・誕生日がGWとかぶってしまうと、毎年どこも混んでいる。
・親の復職のタイミングと、保活の調整がやや複雑なことも。
とはいえ、「工夫次第で乗り切れること」ばかりでもあるので、あまりネガティブにとらえる必要はありません。
どの月にもメリット・デメリットはあり、5月生まれは、比較的「丁度いいタイミング」のように思う人が一定以上いるというだけの話です。
ここで、実際のママたちのリアルな声を聞いてみましょう。
・5月のGW中に臨月でしたが、幼いこどもがいるので、夫が休みだったり、母が長期で手伝ってくれたりと、大人の人手があって助かることをひしひしと感じた。
・連休があり、病院の予約が少し取りづらかった。
・新年度が始まってまだ1か月、誕生日会をするほどまだお友達ができない時期なのは少し残念。
 ちょうどいいイラスト
ちょうどいいイラストまとめ
総じて、どの誕生月が得か、損か考えるより、我が子にあった関わり方をすることが一番大事という意見が多くありました。
出産のタイミングや、保活の時期など、効率的になりすぎず、こういう考え方もあるんだと柔軟に考えておくほうが無難といえるのではないでしょうか。
その時期だからこその楽しみ方がきっとたくさんあるので、子供と一緒にその時期その月齢ならではの過ごし方を楽しんでみてください。
5月生まれはなぜ人気?妊活のタイミングや名づけのヒントを紹介
出産は4〜5月がいい? 待機児童にならないための「10の保活テクニック」を紹介
子どもが『5月出産予定』で良かったこと
あわせてチェック!
「ねえこれ知ってる?」
友だちにも教えてあげよう♪